
これから書くことは、研究途上で気づいた傾向などを紹介するものであり、内容のすべてが正しいとは限らない。
その点を考慮して、なるべくならば一部または全部を転載せずに、リンクを張って紹介していただくことを希望する。
今後、内容を訂正することがあるかもしれないからだ。
【目次】
南海トラフ巨大地震の発生月の偏り
過去の南海トラフ巨大地震の発生の傾向として、奇妙なことがある。
歴史上知られている南海トラフ地震のうち、すべては8月~2月の期間に起きていて(特に12月に集中)、3月~7月の春から夏にかけては起きていないことだ。
このことに強い関心をもって、他の日本で起きた大地震のデータを調べたところ、このような月による偏りは、これほど顕著なものは見られなかった。
各月で、だいたい均等に起きているのだ。
南海トラフ地震だけ、季節によって起きる起きないがあるのだろうか。
あるとしたら、どんな説明原理があるのか。
南海トラフあたりで季節に関係することで頭に浮かぶのは、南海トラフ付近を東へ流れていく黒潮の存在だ。
黒潮と大地震あるいは南海トラフ地震の発生には、何らかの相関関係があるのだろうか。そう、漠然と考えていた。
黒潮の大蛇行
黒潮とは、東シナ海を北上してトカラ海峡から太平洋に入り、日本列島の南岸に沿って流れ、房総半島沖から東へ流れていく海流のこと。
日本近海の代表的な暖流で、日本海流(にほんかいりゅう)とも呼ばれる。
プランクトンの生息数が少なく、透明度が高いため、海色は青黒色となり、このために黒潮と呼ばれる。
南極環流やメキシコ湾流と並ぶ、世界最大規模の海流だ。
黒潮は時として大きく南下する大蛇行流路をとることがある。
大蛇行の頻発する時期(大蛇行期)とそうでない時期(非大蛇行期)は、約20年周期で入れかわるという説がある。
下記の図は、気象庁サイトの「日本近海 日別表層水温」のデータで、2013年8月1日時点のものだが、大蛇行期に入ったことがわかる。
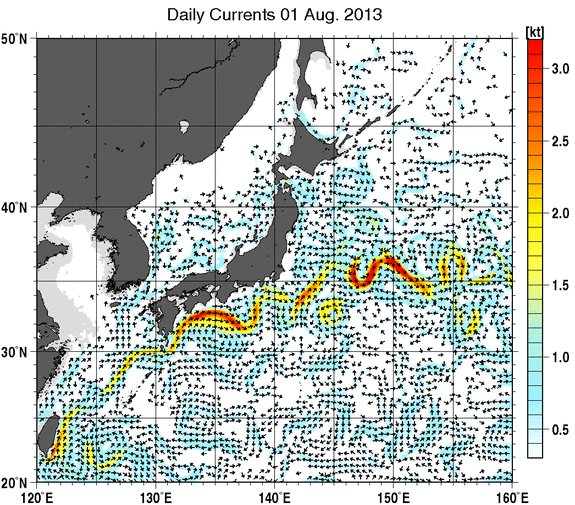
紀伊半島の南沖あたりから南側へ迂回しているのが、それだ。
赤または黄色の部分で、海水温が高いことを示している。
また、下記の2014年9月1日の現時点でのデータを見ると、非大蛇行期に入っていることがわかる。

大蛇行中は、黒潮が迂回している海域で、海水温が低下するという。
太平洋側で深海魚が出現した時には、黒潮の大蛇行期か非大蛇行期かを調べる必要があるだろう。
南海トラフ地震は非大蛇行期に起きやすい?
過去の黒潮の大蛇行について調べていて、1934年または1935年から1944年秋頃まで、黒潮の大蛇行が続いたことがわかった。
1944年といえば、12月7日に昭和東南海地震が起きた年ではないか。
終戦前後には、西日本の太平洋側で以下の3つの大地震が起きている。
1944/12/07 13:36昭和東南海地震M7.9
1945/01/13 3:38三河地震M6.8(三河湾)
1946/12/21 04:19昭和南海地震M8.0
このうち、最初の東南海地震が黒潮大蛇行終了の1~2ヶ月後に起きていることに注目した。
非大蛇行期に入った直後に起きているのだ。
以下に引用するように、南海トラフ地震が、黒潮の直進期(非大蛇行期)に起きやすいという研究がある。
岡田(1978)は、南海トラフのM>6.5の地震を1870年から調べて、地震の発生と潮流の関係を指摘。黒潮は大蛇行期と直進期とを繰り返すが南海トラフの大地震は直進期(非大蛇行期)に発生しやすい。大蛇行期には東海沖で海底面への垂直圧力の変化が生じる。
(「次の南海地震はどのようなものか?」より)
(引用元ページは名古屋大学サーバーより削除されました)
大蛇行期の大地震の発生状況
そこで、過去の黒潮の大蛇行期に西日本から関東までの太平洋側で大きな地震が起きているかどうか調べてみた。
戦後の大蛇行は、以下の6つの例がある。
・1975年8月~1980年3月
◎1978/01/14、伊豆大島近海、M7.0
◎1978/03/07、東海道南方沖、M7.2
・1981年11月~1984年5月
◎1984/03/06、鳥島近海M7.6⇒大蛇行終了直前
◎1984/06/13、鳥島近海M5.9、津波地震150cm⇒大蛇行終了直後
・1986年12月~1988年7月
大地震は特になし。
・1989年12月~1990年12月
大地震は特になし。
・2004年7月~2005年8月
◎2004/09/05 19:07、紀伊半島南東沖地震M7.1⇒大蛇行開始直後
◎2004/09/05 23:47、紀伊半島南東沖地震M7.4⇒大蛇行開始直後
大蛇行開始2ヶ月後、震源は大蛇行で迂回する範囲内で海水温が低かった。
・2013年7月~2014年4月
大地震は特になし。
1984年の2つの鳥島近海の地震が興味深くて、大蛇行終了直前と直後に起きている。
鳥島は、大蛇行によって黒潮が近づくところで、タイミング的にも何かしら影響があったのかもしれない。
2004年の紀伊半島南東沖の連発は、まさに大蛇行で迂回した範囲内にあり、これも大蛇行開始の2ヶ月ほど後で、何かしら関係があるのか。
まるで、黒潮が大地震が起きるところを避けて大蛇行を始めたかのようだが、ちょっと考えにくい。
大蛇行期には、黒潮の影響が出そうな海域では、大きな地震が少なくなる傾向にあるのかもしれない。
あくまでも、非大蛇行期と比較した大雑把な印象によるものだが。
このような傾向が本当にあるならば、南海トラフ地震に限らず、西日本から関東にかけての太平洋側では、黒潮の大蛇行が大きな地震を「抑制」するということがあるのだろうか。
昔の南海トラフ地震と黒潮大蛇行の関係を調べたいところだが、大蛇行が発見されたのが1930年代だから、そんなデータはどこにもない。
ここで書いた法則が成り立つとすれば、今年4月以降は非大蛇行期に入っているので、特に8月~2月が、南海トラフ地震が起きる条件はあるということになるが、さてどうなるか。
いつ起きるかまったく見当がつかないというよりは、絞り込めた方が心の準備ができるだろう。
あくまでも、本当だとしたらの話だが。
【追記】2014/09/14
過去の日向灘地震について調べていたら、1984/08/07にM7.1の地震が起きていたことがわかった。
これも黒潮大蛇行の期間外で、しかも1984年5月に大蛇行が終わった直後に起きている。
この記事で書いたことを、以下にまとめておく。
◎南海トラフ地震が起きる可能性が高いのは、8月~2月で、特に12月に多い。
◎南海トラフ地震は、黒潮の非大蛇行期に起きる可能性がある(百瀬)
◎南海トラフ地震を含めて、大蛇行期には太平洋側の地震が抑制される?(百瀬)
◎深海魚の出現と地震の関係を考慮する際に、黒潮など海流の状態と海水温を考慮する必要がある。
あくまでも可能性として書いたまでだが、今後も研究を続けることにしたい。
※地震前兆ラボの「リアルタイム地震前兆データ」に、「日本近海 日別表層水温(マップ)」と、黒潮の変化がわかる「日本近海 日別海流(マップ)」を追加しました。
【参考】
・海軍水路部における海洋観測と当時の日本南岸域の海況について
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/KENKYU/report/tbh22/tbh22-09.pdf
・黒潮大蛇行と南海トラフ地震の研究
https://kaken.nii.ac.jp/d/p/16340126.ja.html

- 作者: 日高旺
- 出版社/メーカー: 南方新社
- 発売日: 2005/01/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

- 作者: 日本科学者会議
- 出版社/メーカー: 本の泉社
- 発売日: 2014/03/05
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログ (1件) を見る

南海トラフ巨大地震――歴史・科学・社会 (叢書 震災と社会)
- 作者: 石橋克彦
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2014/03/12
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る

NHKスペシャル MEGAQUAKE III 巨大地震第4回 南海トラフ 見え始めた“予兆" [DVD]
- 出版社/メーカー: NHKエンタープライズ
- 発売日: 2014/01/24
- メディア: DVD
- この商品を含むブログを見る
【龍矢】【愛弥美】西武遊園地に来ています。At Seibu Playpark.
【龍矢】初めてのプールで大はしゃぎ。First experience of a pool.
【愛弥美】西武ゆうえんちプールで初めて足が水に浸かっただけでブルブルして泣き出した。水に浸かった経験がないから仕方ないか。Ayami started crying, being afraid of water.
【愛弥美】ひよこクラブにモデル募集で送った写真が没の雰囲気で、送った写真が悪いとサルちゃんからクレームが出た。^^;Ayami at Seibu Playpark.




