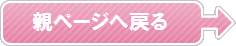このページでは、主にコイの前兆現象を紹介する。
川・池・沼に生息するコイ(鯉)とフナ(鮒)は、いずれもコイ目コイ科コイ亜科に分類される魚なので、一部の例ではフナも扱うことにする。
戦前の事例
コイ(鯉、学名:Cyprinus carpio)は、コイ目・コイ科に分類される魚で、比較的流れが緩やかな川や池、沼、湖、用水路などにも広く生息する淡水魚である。
最初に、亀井義次氏の『大地震前兆集』で紹介されている例をいくつか挙げておく。
1923年(大正12年)9月1日の関東大震災(M7.9)が起きた日の朝7~8時頃、東京・千住東町の池の水面に、コイやフナがことごとく浮き上がった。
近所の人々がすくい取り、井戸水に入れておいたら元気を取り戻したという。
1939年(昭和14年)5月1日に秋田県の牡鹿半島で発生した男鹿地震(M6.8)では、前日に八郎潟の岸に多くのフナやコイが群がり、釣るといくらでも釣れるので、森岳駅の駅長は気味が悪くなって釣りをやめたという。
戦後の事例
篠崎幸弘という男性が子供の頃に、関東大震災の前に池のコイや金魚が浮いて息絶えていたのを見たことを、1979年に業界新聞で書いている。
宮城県沖地震(著者注:1978年6月12日のM7.4の地震と思われる)の2~3日前から、仙台市のある家の池のコイが暴れて、芝の上に飛び出すのもいたという。
金魚など他の魚が飛び出る場合でもそうだが、察するところ、パルス電磁波によって水中に流れる電流によって痛みを感じ、たまらずに飛び出すのかもしれない。
1978年1月14日の伊豆大島近海地震(M7.0)では、4日前頃から、冬眠中のはずの池のコイ9匹すべてが、活発に動き始めたという。
地震の後には静かになり、もとの冬眠状態に戻った。
逆に、水底でじっとしていたというのならば、コイやフナも冬眠する魚なので、地震とは関係ないことになるだろう。
阪神・淡路大震災(1995)
1995年1月17日の阪神・淡路大震災の前には、日付は書かれていないが、大阪府吹田市で池のコイがすべて同じ方向を向いて整列し、不気味なほどの情景だったという報告がある。
これもキンギョと同様に、パルス電磁波の電場に対して垂直の方向に向くと、体内を流れる電流が軽減されることを経験的に知っているためと思われる。

キンギョの項で書いたように、神戸市では地震の3日前からキンギョ、ドジョウ、コイ、ナマズが一切餌を食べなくなり、泳ぐこともなくなった。
兵庫県三田市では、地震の2日前に、庭の池で冬眠していたニシキゴイが、全部池の中層で動きまわっていた。地震の後はまた冬眠に戻ったという。
熊本地震(2016)
これは2016/04/11の探求三昧ブログの記事で書いた内容だ。
Facebookの非公開グループである「地震前兆・体感検証」の投稿で、2016/04/09 13:00頃から、大阪で大量の鯉が現れ、暴れていたという。
ただそれだけだが、地震前兆だとすれば、パルス電磁波により水中に電流が発生し、それに耐えかねて飛び跳ねたりしていたのかもしれないと私は書いておいた。
その5日後の2016年4月14日21時26分に、熊本地震の前震であるM6.5、最大震度7の地震が発生した。
更に、2016年4月16日1時25分に、M7.3、最大震度7の本震が発生した。
4/9の大阪でコイが暴れていたという現象は、地震の規模、震源までの距離、タイムラグを考慮すると、熊本地震(前震と本震)の前兆現象だった可能性は高いだろう。
まとめ
・暴れて飛び跳ねる(3日前)
・同じ方向を向き整列する
・冬眠から目覚めて活発に動き出す(4日~2日前)
・よく釣れる(1日前)
【参考文献】

地震の確率―ヘビやネズミは知っている! (Nesco books)
- 作者: 力武常次
- 出版社/メーカー: ネスコ
- 発売日: 1986/01
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る

前兆証言1519!―阪神淡路大震災1995年1月17日午前5時46分
- 作者: 弘原海清
- 出版社/メーカー: 東京出版
- 発売日: 1995/09
- メディア: 大型本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 亀井義次
- 出版社/メーカー: 徳間書店
- 発売日: 1983/03
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (1件) を見る